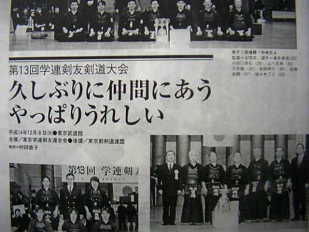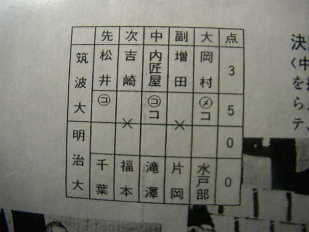| 榛高剣道部と私 |
| 100周年 中日新聞掲載記事(H12,9/27) |
| 榛原高等学校の歩み 至誠真剣 第2部 卒業生は語る。 |
| 松井 美喜雄 榛原高校剣道部顧問(H4〜H14) |
勝敗だけではなく人生を学ぶOBら合宿で後輩指導 |
| 昭和40年代の榛原高校剣道部の活動は、やりたい者だけがやるという時代であった。 現代のような技術指導法も確立されておらず、お互いが工夫しながら剣道を楽しん だ時代でもあった。大会数・参加校も少なく、勝負にこだわることもなく、余力をもっ て活動していた。大学に進学した者の多くが剣道を継続して活躍し、静岡県に榛原 高校ありを示した。 その基礎が確立されたのは1958(昭和33)年、秋野佐一郎(前榛原高校教頭)の ご尽力により、旧榛中の基盤の上に新しい花を咲かそうと、OB会「剣親会」が結成 されたことによる。1959年には小形澄夫、秋野佐一郎両先生の出身校で尾崎敦 氏が所属している國學院大學剣道部の方々がコーチに来てくれた。榛原町の講堂 に泊まり込んで合宿が持たれ、昼夜の講義と歌(大学の部歌)には皆、真剣にかつ 楽しく聴き入った。この先輩達にあこがれて大学への進学を決めた者も多かった。 1960,61年に2年連続で全国大会ひ駒を進めた澤入辰義氏(現剣親会会長)を はじめ、大窪欽也氏は國學院大、鈴木誠士郎氏は立教大ひ、さらに1963年、戦 後3回目の全国大会出場のメンバーである三井敏明氏は亜細亜大、柴信孝氏は 専修大、先生(せんじょう)喜彦氏は芝浦工大、松尾郁夫氏は國學院大、筆者は 東京教育大に進学した。三井氏は関東大学選手権の個人戦で優勝し、また、筆 者は同じく3位と団体戦ではインカレ(全日本大学選手権大会)優勝のメンバーに なった。 昭和40年代は松井浩憲氏(駒沢大)、松井秀浩氏・柴貴氏は(國學院大)、相羽 広志氏(専修大)たちが進学後、各大学のリーダーとなり活躍した。これらのメン バーが昭和42年(1967)、小形先生転任後も春夏の榛原高校の合宿に、はせ 参じては後輩を指導した。 昭和39(1964)年には、榛原高校剣道部に最初の女子部員、鈴木(内藤)公子、 植田(横山)緑、小泉啓子の3氏が入部した。剣道は男子の運動部という意識が 強かっただけに戦前・戦後を通し画期的なことであった。この年を境に女子剣道の 大会が開始され、現在の女子剣道の隆盛へと発展することになった。 昭和42(1967)年度卒の早川和幸氏は「勉強専念のために多くの仲間が道場を 去っていった。現在も文武両立に悩む者が多いと聞く。安易に自分の進む道を決 めてしまわぬよう、まして練習の辛さや遊びたい自由な時間欲しさのためだけに貴 い部活動を捨ててしまうことがないように祈りたい」と榛高80周年記念の「榛高剣 道史」で語っている。 現代の剣道は全国的規模での大会・交流会が多く持たれ、「競技剣道化」の傾向が あるが、勝敗だけでなく「人生」を伝え、「日々流汗之行」が脈々と受け継がれていく 榛原高校剣道部であってほしい。 |