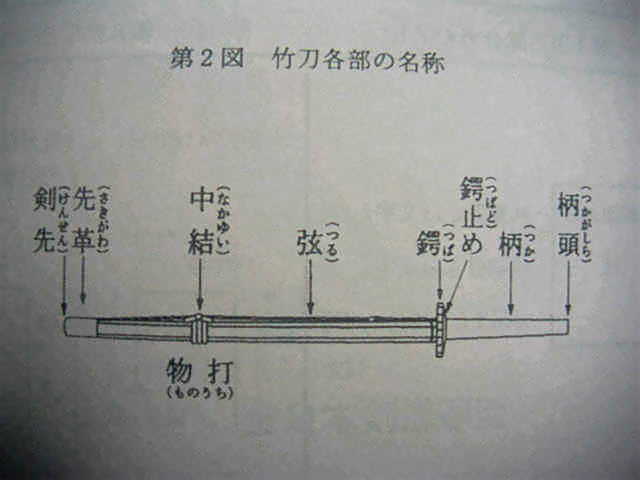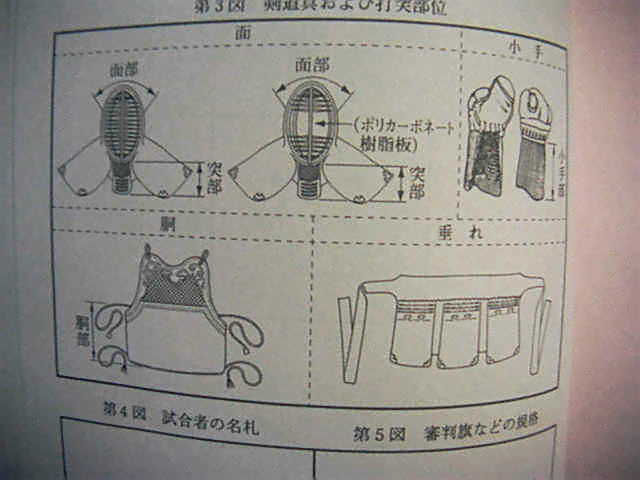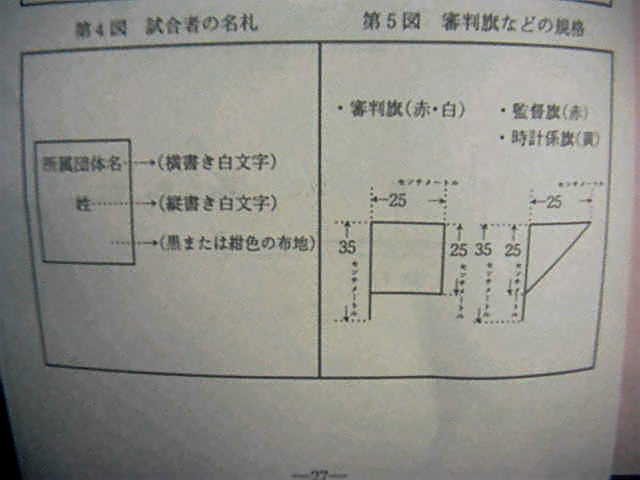| 第1条 本規則の目的 この規則は 全日本剣道連盟の試合規則につき、 剣の理法を全うしつつ、 公明正大に試合をし、 適性公平に審判すること を目的とする |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剣の理法について参考( 剣道問題集 剣道講習会 ) 講習会におけるへ 試合 審判 運営の手引き の 規則 審判の 一規則へ (審判は 第1条(本規定の目的)を基本にして・・・・ ・・・・) 審判規則の改正と運用上の要点 第1条 剣の理法を全うしつつ、という教育的要素を盛り込み 試合と審判に関する規則の目的を明確にした ・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 試合場 (床は板張り原則とする) 基準 ①境界線を含み 一辺 9m~11mの正方形か長方形 ②中心は × 印 開始線は 中心線より均等の位置(距離)に表示 開始線の長さ 及び 開始線間の距離は細則で定める ・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審判規則の改正と運用上の要点 第2条 開始線を設けることとした 試合者が試合開始に当たり その宣告と同時に打突することや 直ちにつば競り合いに入る行為があったことに かんがみ 適正な間合をもって試合開始することを主眼とし 審判の宣告の際に 試合者相互に適正な間合をとらせることをも併せて目的として 設けたものである ・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1編試合 第1章総則 試合場 細則第1条 ・ 規則第2条 試合場 ①試合場の外側に原則として 1,5m以上の予知を設ける ②各線は 幅 5~10cmとし 白線を原則とする ③試合場の中心( ×印 ) 開始線の長さ 開始線間の距離は 第図1参照 ・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||