 |
内側より小太刀 太刀 刃は自分の方向 刀は こじりより床に(音がしない) 柄が前 天覧台覧は刃部下 切っ先前下がり 座して 小太刀 太刀を持つ 上座30度 お互い15度の傾け礼 |
| 1本目 | 中段の構え 右足を前に 左拳は臍前より 一握り前にして 左手親指の第一関節を臍の高さに剣先の延長は、両眼の中央または左目とする(一足一刀の間合を前提にする) |
 |
9歩の間合 剣先は膝頭下 約3〜6センチ 構えを解く 自然に相手の左膝頭から 約3〜6センチ下 下段の構え 程度に右斜め下に下げる この時 剣先は相手の体から わずかに外れる位 開き 刃先 は左斜め下を向く |
 |
← 1本目 左額の前 諸手左上段 左頭部、約一握り 45度 |
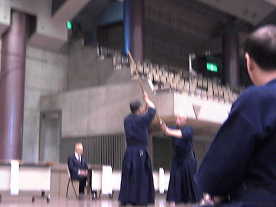 |
柄 もろとも臍下まで切り下げる。 打ち下ろした剣先は下段の構え からやや低くなる (次の写真 参照) |
| H14 仕太刀の柄もろとも打ち下ろす 気構えが大切である 理由 「うち下ろした剣先は、 下段の構えからやや低くなる」 を削除した。 |
その理由 打太刀の その後の動きについて 本文に「打太刀が剣先を下段のまま送り足で一歩引くので」とあり、また最後の動作の説明打太刀が剣先を下段から中段につけ始める・・・」となっていることなどから、打ち下ろしは、下段の構えの剣先の高さ程度で一本目の打太刀に大切なものは、機を見て、仕太刀の 柄もろともに打ち下ろす気構えであって、その後の余勢で下段より低くなることもあると解する方が妥当との 結論により削除した。 |
1 |
一本目 ヤー の 後 仕太刀 斜め上に抜く そして トーへ移る 抜いた角度に 注目する また 打太刀 ヤーの後の 剣先 膝下まで 切り下げている 高さに注目する |
 |
H14 |
| 仕太刀 残心 打太刀は 首が下がるほど前傾はしない |
|
| ・ |





